🎃【本当は怖い?心温まる?】日本と海外のハロウィン、文化の違いに見える「人とのつながり」

ハロウィンって何のためのお祭り?
10月に近づくと街にはオレンジや黒、パープルの装飾が並び、ジャック・オー・ランタンや魔女、ガイコツのグッズがどこかしこに。仮装イベントや限定スイーツも出回り、ちょっとワクワクする季節です。
「ハロウィン=仮装して楽しむお祭り」と思っている方も多いでしょう。でも、それって実は”日本的ハロウィン”。本来のハロウィンにはもっと深い意味があるのです。
もともとは“先祖と向き合う日”だった
ハロウィンの起源は、古代ケルト民族の収穫祭「サウィン祭」。現代でいうアイルランドやスコットランド周辺の人々が、「10月31日は霊界と現世の境界が薄れる日」として、死者の魂を迎える特別な時間として過ごしていました。
彼らは死者を敬いながらも、迷える霊が災いをもたらさぬよう、仮面をかぶって身を守っていたのです。いわば、ハロウィンは「死と生をつなぐ夜」でもありました。
アメリカでは“地域の絆を育むイベント”に
アメリカではこの風習が少しずつ形を変え、19世紀中頃にアイルランド移民の文化とともに定着しました。
今では、「トリック・オア・トリート!(お菓子をくれないとイタズラするぞ!)」の合言葉と共に、子供たちが仮装して近所を訪ね歩きます。お菓子を用意して待ち構える家庭も、ハロウィンの醍醐味のひとつ。
日本で言う“町内会”のような、近所とのつながりを再確認できる、地域密着型の文化行事として定着しています。
一方、日本のハロウィンは“大人のフェス化”?
では、日本ではどうかというと、仮装イベントやパーティー中心。「渋谷のコスプレ大行進」や、テーマパークでのイベントがその象徴ですね。
もともとは1970年代に洋菓子店が“秋の販促イベント”としてハロウィンを採り入れたのが始まり。そこにテレビやSNSの拡散が加わり、仮装ブームと一体化したのが今のスタイルです。
つまり、日本では「楽しさ」や「非日常体験」に主眼が置かれていて、本来の宗教的・文化的意味合いはほとんどありません。
メキシコでは“死者と過ごす祝祭”
ハロウィンに似た文化は他の国にもあります。
メキシコでは「死者の日(Día de Muertos)」と呼ばれ、10月31日から11月2日にかけて故人の魂を迎える行事が行われます。祭壇には亡き家族の好物や花、写真が並べられ、家族みんなで過ごす温かな祝祭です。
映画『リメンバー・ミー(COCO)』を見たことがある人は、あの色とりどりのパレードやガイコツの装飾を思い出すかもしれません。あれが、まさにメキシコの「死者を敬う文化」なのです。
日本と海外、どちらが正しいの?
正解はありません。ただ、それぞれの文化の背景や価値観によって、同じ日でも意味や楽しみ方が違うのです。
日本のハロウィンも“悪くない”。大人が日常を忘れて仮装を楽しむのも、ストレス社会においてはむしろ必要な時間かもしれません。
ただ、海外のように「人とのつながり」「世代間の交流」「亡き人との対話」といった側面も加われば、もっと“深み”のある行事になるのでは?とも思います。
ご近所ハロウィン、やってみたい
個人的には、アメリカのように子供たちがご近所を回ってお菓子をもらうようなハロウィン、すごく素敵だと思います。
子供が主役になり、大人もそれを温かく迎える。そして1人暮らしの高齢者も、玄関先で小さな魔法使いやドラキュラに出会い、思わず笑顔になる……そんな地域のぬくもりを感じられる日になったら、最高ですよね。
色にも意味がある!ハロウィンカラーの豆知識
街中のハロウィン装飾に見られる「オレンジ・ブラック・パープル」。
-
オレンジ:秋の実り、太陽の象徴。ポジティブなエネルギー。
-
ブラック:死、闇、未知の世界。魔よけの意味合いも。
-
パープル:神秘、月の光、夜空。霊的世界との境界線を象徴。
何気なく見ている色にも、実はスピリチュアルな意味が込められているんですね。
ハロウィンをもっと“自分ごと”に
これからの日本のハロウィンは、ただのコスプレイベントだけではなく、「人とつながる日」「死者を思い出す日」「家族や地域と再び交わる日」にしていけたら面白いと思います。
誰かと笑った記憶、手を振ってくれた子供の姿、亡き家族と交わした温かい記憶。そんな“思い出”を育む一日になれば、ハロウィンはもっと豊かで意味のあるイベントになるはずです。
🎃まとめ:ハロウィンで「人との距離」がちょっと縮まる
今の日本のハロウィンも楽しいけれど、少しだけ“本来の意味”に立ち返ってみませんか?
-
子供と過ごす
-
亡き人を思い出す
-
ご近所に声をかける
-
色の意味を知る
そんな新しい“気づき”を加えれば、10月31日は単なるコスプレ大会じゃなく、「心のつながり」を再確認する特別な1日になるかもしれません。
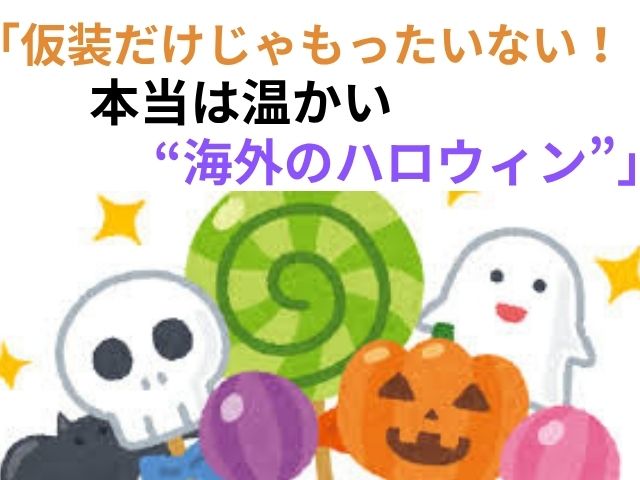

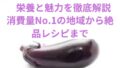
コメント